この記事では、看護師の申し送りを上達させる方法を紹介します。
看護師の申し送りは、避けては通れないもの…
新人看護師の中には、苦手意識を持つ人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、12個のポイントを元に申し送りを上達させる方法を紹介します。
また、よくある状況を設定して、上手な申し送りの例文も載せました。
申し送りに悩んでいる看護師さん、必見です!
1.看護師の申し送りとは?

看護師の申し送りの目的は、ざっくり分けると以下の3つです。
| 看護師の申し送りの目的 |
|---|
|
自分の勤務は終わっても患者さんへのケアは次の勤務者によって継続され、また次の勤務者へ引き継がれていきます。
申し送りは、患者さんの1日の流れを継続的に支援するために必要なものなのです。
正確な情報共有は、看護のレベルを同一に維持するために必要不可欠です。
また、次の勤務者がスムーズに業務に臨めるよう簡潔で的確な申し送りが求められます。
2.看護師の申し送りが下手な人の共通点

申し送りが下手な人の共通点を以下に挙げました。
| 申し送りが下手な人の共通点 |
|---|
|
新人のうちは、申し送りのはずがいつの間にか知識確認の時間になっていた、なんてことも。
「また答えられなかったらどうしよう・・・」と思うばかりに、全てをありのまま伝えようとします。
すると、話は長くまとまらず、「で、何が言いたいの?」となるわけです。でも大丈夫。
申し送りの方法は学校で習いませんし、現場に出ると専門用語は一気に増えるしでうまくできなくて当然です。
先輩のやり方を真似したり、ここで紹介するポイントを参考にしながら一緒に練習しましょう。
試行錯誤は改善への近道です!
3.看護師が上手な申し送りをするためのポイント12選

この章では、看護師が上手な申し送りをするためのポイントを紹介します。
今回紹介するのは、以下の12個です。
早速、それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1.出来る限り簡潔に必要な情報を申し送る
SBARという報告方法を知っていますか?
内容は下記の通りです。
| SBARとは? | |
|---|---|
| Situation(状況) |
|
| Background(背景) |
|
| Assessment(評価) |
|
| Recommendation(提案) |
|
これは医師への報告の際に用いられることが多い方法ですが、このツールを用いる目的は簡潔かつ明確に、正確な情報を相手に伝えることです。
これを看護師間の申し送りで意識してみましょう。
日々の申し送りがSBARの訓練にもなりますよ!
3-2から3-7がそれぞれSBARにどう当てはまるか考えながら読んでみてください。
3-2.輸血などをした時はHbの値も確認して伝える
輸血が終わっているのであれば、行為だけでなく結果も引き継いだ方が丁寧です。
先輩看護師であれば、輸血していると分かった時点で投与前後のHb値はカルテで把握していると思います。
なぜ輸血が必要だったのか自分自身も理解しておくと、申し送り内容で伝えるべきことが見えてきます。
3-3.状態変化があった日のことは時系列で話す
現在の状況までに至る過程を簡潔に引き継ぎましょう。
状態変化があったということは治療薬などが追加・変更になっている可能性もありますね。
時系列で話すことで、医師の考えも伝わりやすくなりますよ。
3-4.状態が悪い人は血圧や尿量、意識レベルも合わせて申し送る
状態が悪いということは、急変のリスクが高いということです。
勤務者が変わっても、常に同じレベルの看護を提供する必要があります。
どの状態まで医師に報告してあるのか、次回報告のタイミングなども併せて申し送りましょう。
3-5.微熱や高体温の患者さんがいた時は最終の体温と計測時間、発熱時の指示も伝える
これらの申し送りは、次の勤務者が実際に検温に行った際のアセスメントに重要な情報です。
もし数日前から出ている発熱時の指示内容が変更になった際には、その経緯を引き継ぐと、医師の考えも伝わるのでより親切です。
3-6.頓用薬の必要な患者さんの申し送りは頓用薬の使用の有無と最終使用時刻も伝える
頓用薬は1日の使用上限や、使用間隔が決まっています。次の勤務者が頓用薬を使う際、最後いつ使用したかというのは重要な情報です。
時間がさほど空いていないなら、状況報告とともに別の指示を医師に仰ぐこともできますね。
確実に引き継ぎましょう。
3-7.転倒した人や転びそうな人はその人のADLと転倒予防の対策、ベッド周辺の状況を伝える
転倒した人はその原因を、転倒リスクのある人はその傾向を申し送りましょう。
これらの情報は、転倒予防対策の根拠になります。
転倒事故防止に大切なことは「傾向と対策」です。継続した転倒予防のために日中の様子などを引き継ぎましょう。
3-8.申し送りが上手な人の言葉を真似する
申し送りが分かりやすいと感じる人がどんな申し送りをしているか研究してみましょう。
複数人いる場合でも共通点があるはずです。
ポイントは以下の3つです。
| 申し送りが上手な人のここを見ろ! |
|---|
|
3-9.申し送るべきことをメモするか、マーカーを引いておく
勤務中は業務が重なり、ゆっくり記録する時間が取れないことは多々あります。
申し送るべきことだと思ったらすぐメモを取るかマーカーを引いて分かるようにしておくことがおすすめです。
あとで記録する際にも役立ちますよ。
3-10.緊張するのであれば申し送る内容を書き出しておく
自分でも何言ってるか分からない時ってありませんか?
内容に一貫性がなかったり、情報があっちこっちに飛んでいると聞き手は非常に疲れるものです。
申し送りたいことを箇条書きにして書き出しておくと要点を把握できるのでおすすめです。
3-11.申し送りをイメージトレーニングする
申し送りたいことを書き出したら、それを見てスムーズに申し送りできるか事前に予行練習してみましょう。
難しそうだと思ったら文章を作ってメモにしても大丈夫。
慣れないうちは、自分なりの申し送りテンプレートを作成するのもありです。
3-12.常にどうすれば聞き手がわかりやすいかを考え工夫する
ニュースなどを見ていて、出演しているコメンテーターが結局何を言いたいのか分からなかったという経験はありませんか?
逆に、発言時間は短いのにとても分かりやすいと感じる人もいますよね。
この違いは何か観察し、取り入れることもおすすめです。
4.先輩看護師から申し送り中に突っ込ませない3つのコツ

この章では、先輩看護師からの突っ込みをなくすためのコツを紹介します。
| 先輩看護師から申し送り中に突っ込ませないコツ |
|---|
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1.普段から信頼を獲得できるように動く
失敗は誰にでもありますが、同じことを繰り返さないことこそ信頼を獲得できる近道です。
例えばあなたが申し送り中、先輩に突っ込まれすぎてなかなか終わらなかったとします。
曖昧な態度は不信感に繋がるので、分からないことに対しては「確認して後ほど報告します!」で、回答を避けましょう。
そして、突っ込まれたことをメモなどに整理し、次回の申し送りに活かしましょう。
4-2.看護記録などを入念に記録し、できるだけ抜けがないようにする
看護記録は次の勤務者が来る前に仕上げたいところですが、なかなか難しいですよね。
なので、最低でも経過表だけは完成させておきましょう。
おそらくどの施設でも、経過表に患者さんの状態に合った観察項目が盛り込まれていると思います。
経過表は医師も確認するものなので、これだけはタイムリーに埋めておきましょう!
4-3.先輩と関係を築く
看護師の仕事は一人で成立するものではなく、常にチームで動いています。
「私の受け持ちハードすぎない・・・?」と思うこともありますが、自分が気づかぬうちに先輩が手伝ってくれていることが多々あります。
気づいた時点ですぐに感謝の気持ちを伝えましょう。
逆に、自分の手が空いている時には「私に何かできることはありませんか?」と声をかけにいくと好印象です。
また、怖い顔で何か指導されても、叱られたとしても、最後に「教えてくださってありがとうございます!」と一言伝えると良いですよ。
5.【状況別】看護師の上手な申し送り例
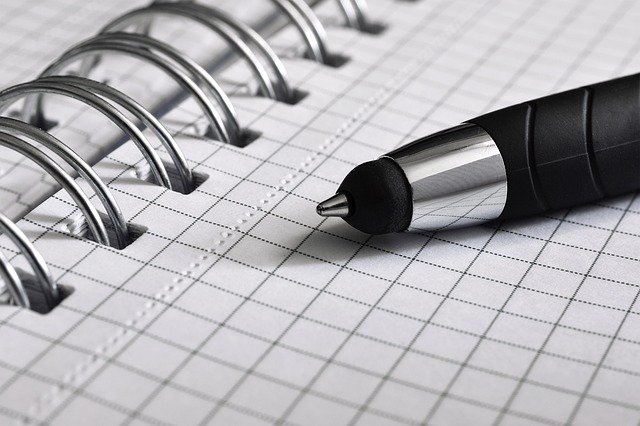
この章では、よくある状況別に、上手な申し送りの例を紹介します。
ここで設定する状況は、以下の5つです。
| 【状況別】上手な申し送り例 |
|---|
それぞれ詳しく見ていきましょう。
5-1.入院の日・転棟してきた日
5-2.検査・手術があった日
5-3.発熱した日
5-4.絶食となった日
5-5.転倒・転落した日
6.看護師の申し送りに関するよくあるQ&A

この章では、看護師の申し送りに関するよくあるQ&Aを紹介します。
今回紹介するのは、以下の5つです。
| 看護師の申し送りに関するよくあるQ&A |
|---|
上記に気になる質問があれば、見てみましょう。
6-1.看護師の申し送りはどの程度短縮すべき?
近年では申し送りの是非について看護研究で取り上げられ、実際に申し送りを廃止する医療機関も多くなってきています。
記録を読めば分かることをあえて説明する必要はありません。
その分記録は漏れなく記載し、誰が読んでも分かるように気を付けましょう。
6-2.看護師の申し送りで話すべきことの基準は?
記録が間に合わず記載できていないことは申し送りで話すべきです。
また、医師の指示に変更があった場合には次の勤務者と確認会話しておくとインシデントの防止に繋がります。
話すべきことの基準をいくつかピックアップしてみたので参考にしてください。
| 申し送りで話すべきことの基準 |
|---|
|
6-3.看護師の申し送りで話すべき項目ってある?
患者さんの状態によって様々ですが、共通点は以下の通りです。
| 申し送りで話すべき項目の共通点 |
|---|
|
7-2も併せてチェックしてみてください。
6-4.看護師の申し送りが怖い時はどうすれば良い?
申し送りの際、反応が薄くて聞いているのか聞いていないのか分からない人っていますよね。
そしてその態度に萎縮してしまい、どんどん緊張してしまう気持ちもよく分かります。
ですが、そういう相手の場合には聞いていなくてあとで困るのはその人なので、割り切って必要な情報を伝えることに集中しましょう。
6-5.看護師の申し送りはなぜ必要なの?
7-1で、申し送り廃止の流れがあるとお話ししました。
これは看護記録がしっかり記載されていれば、申し送りの一番の目的である正確な情報共有が達成されるからです。
それでも完全になくならないのは、申し送りには重要事項の確認会話や、メンバー同士のコミュニケーションの側面を持ち合わせていることが挙げられます。
施設によって様々ですので、自分が所属している病棟での申し送りの目的を理解しておくと良いですよ。
7.看護師の申し送りに苦手意識を持つ人が読むべき本3選
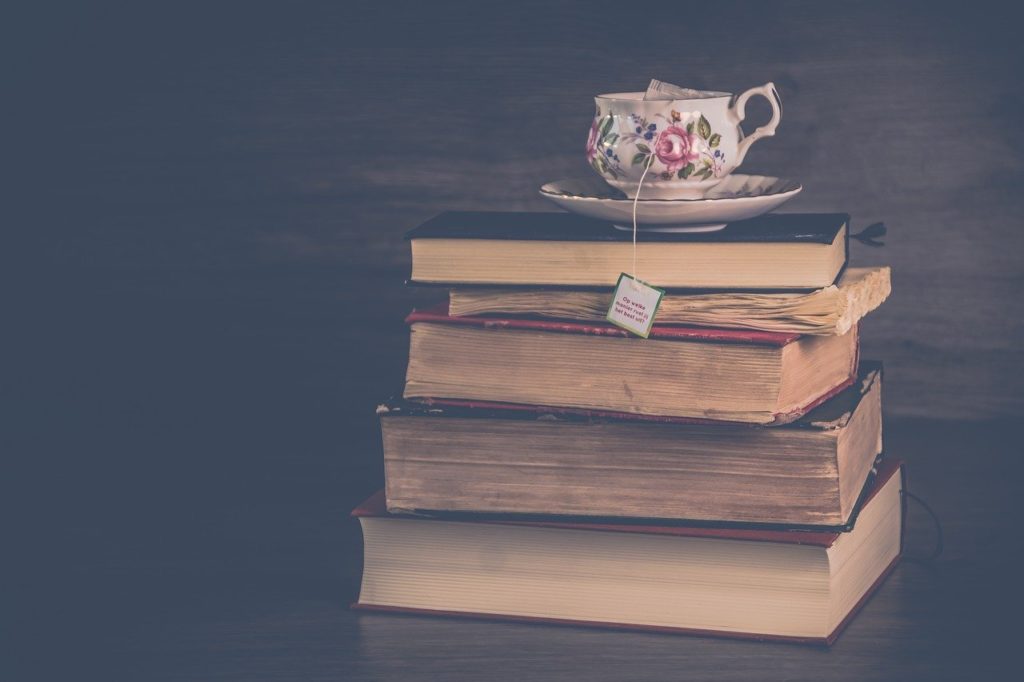
この章では、申し送りに苦手意識を持つ看護師さんにおすすめの本を紹介します。
今回紹介するのは、以下の3つです。
| 申し送りが苦手なら読むべき本 |
|---|
気になるものがあれば、読んでみましょう。
7-1.知識と実践がつながる看護学生のためのコミュニケーションLesson|コミュニケーションスキルを見直そう!
こちらは看護学生を対象とした本ですが、新人看護師の方も指導者の方にもおすすめです。
分厚くないですし、マンガも用いられているのでサクサク読み進めることができます。
信頼を得るための話し方、聞き方のコツなどが掲載されています。
7-2.看護コミュニケーション:基礎から学ぶスキルとトレーニング|コミュニケーションを実践的に学ぶ本!
この参考書の、特に第11章が看護師間の申し送りや医師への報告時に活きてきます。
報告、連絡、相談の重要性が説かれています。「コミュニケーションってどう勉強したらよいのか分からない」という方におすすめ。
ぜひ本屋さんなどで手に取ってみてください。
7-3.こんな看護師は100%嫌われるーチーム医療を円滑にするための医師とのコミュニケーション術|嫌われない看護師になる!
看護師の申し送りに直接役立つ本ではないかもしれませんが、チーム医療を進めていくために必要なことが書かれている1冊。
医師目線で語られているからこそ、看護師の報告の問題点に説得力があります。
医師への報告だけでなく、怖い先輩への報告対策にもおすすめ!
短いので気負わずに読めますよ。

